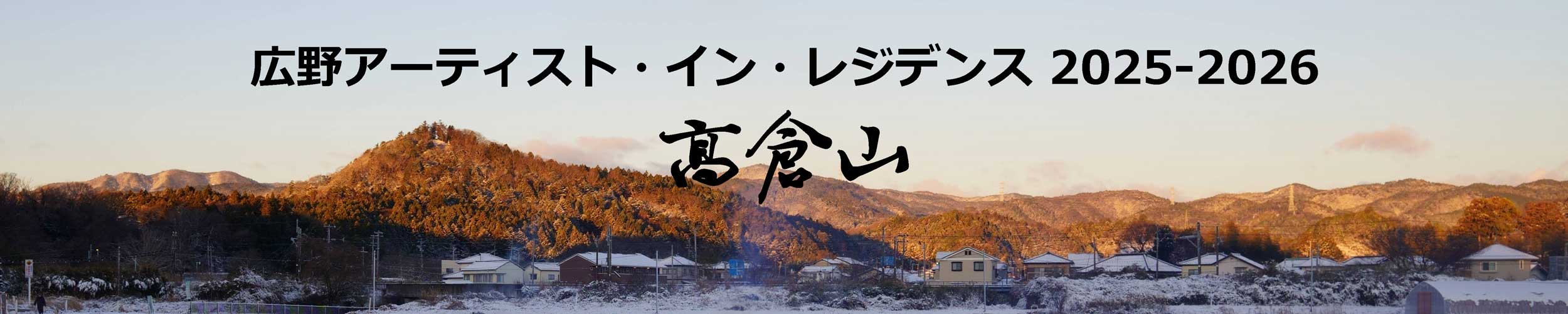リサーチベースドアート (Research Based Art) とは
名前の通り、調査(リサーチ)をもとにして作られたアート作品のことです。どんなアート作品も下調べは必要なものですが、現代アートが社会問題をテーマにするようになってからこの下調べの段階が大きくクローズアップされるようになり、出来上がった作品をプレゼンするときにどんな調査をしたのかをアピールするタイプの現代アートをリサーチベースドと呼ぶようになりました。
時代的には1990年代以降の、文化人類学や社会学のフィールドワーク技法が現代アートに取り入れられた時期以降に一般化したものです。
一つ注意点として、日本語で「リサーチベースドアート」を検索すると「アートベースリサーチ(ABR)」の解説が大量にヒットしますが、ABRはリサーチベースドアートとは全く違うものなので、気を付けてください。(ABRは研究者がアートを使って調査をするというコンセプトです)
リサーチベースドアート:成果物はアート作品
アートベースリサーチ:成果物は論文
どんなリサーチ手法があるのか
| 名前 | 何をするのか | 注意点 |
| インタビュー | 色々な人の話を聞いて記録する | まずは仲良くなってから。集めた情報をそのまま公開するのはNG! |
| 参与観察 | 調査対象の人たちがやっているあれこれを手伝いながら、情報収集する | まずは仲良くなることに集中。集めた情報をそのまま公開するのはNG |
| 文献調査 | 本や雑誌記事、新聞記事を調べる | ウェブ検索よりも紙の情報源の方が圧倒的に大事。図書館や地域の歴史研究家を頼ろう。 |
| 野外調査 | 町や野山を歩きながら資料(石や土、植物、動物、虫など)を集めたり写真を撮ったり野外録音をしたりする。RaspberryPiやM5stackなどのマイコンボードを活用するのもあり。 | 広野町もクマが出るので万全の対策必須。私有地に立ち入る際には許可を取る。 |
| 博物館調査 | 現地の博物館や資料室に収集されている資料(化石や土器、石器、民具など)を見学 | |
| 実験 | 作品に使用する素材を実験によって開発する、何らかの活動や行為を実験として行うなど。 | 実験では特に安全性に注意する。心理学的実験では専門家による指導や研究機関の倫理委員会による事前の実験倫理審査が極めて望ましい。 |
広野アーティスト・イン・レジデンスではこれまでにもインタビュー(「鳥小屋」プロジェクトで津波についてインタビュー)や文献調査(「日の出の松」)、野外調査(ナディン・バルドウ)、博物館調査(「鳥小屋」プロジェクトで古民具などを見学)、実験(鈴木萌子による広野町で手に入る材料を使った紙づくり)が行われてきました。
学術研究との違い
学術研究では調査の結果は論文にして発表しますが、リサーチベースドアートでは調査の成果を使ってアート作品をつくります。学術研究では論文にする段階で「問い」と「答え」がセットになっていますが、リサーチベースドアートでは通常は「問い」だけを作品にします。「答え」は作品に接した人がそれぞれ探してくださいという形です。
リサーチベースドアート企画の考え方:自分の「型」を持つか、「切り口」を探すか
リサーチベースドアート専門のアーティストは自分の「型」を持っている
自分のリサーチの形が完成しているようなアーティストであれば、自分がこれまでやってきたことを対象地域で展開する企画を書くことになります。例えば「鳥小屋」プロジェクトのナディン・バルドウさんは対象地域の野外調査で収集した動植物の標本資料を使って作品を作るスタイルなので、広野町では「津波が到達した範囲に落ちている木々」を集めていました。現在アーティスト・イン・レジデンスをしているパリではカラスの羽根を毎日拾い集めているようです。アイスランドでは動物の骨を集めていました。
こうしたスタイルが確立していないアーティストの場合、自分の興味関心があるキーワードをもとにしたインタビューや参与観察を重ねることで、リサーチを進める形になります。金藤みなみさんは裁縫というキーワードで広野町内でインタビューや参与観察を繰り返しながら情報を集め、人脈を広げていきました。
ただ、こうしたアプローチは「自然と人間の関係をフィールドワークしながら調べて大型スカルプチャーを作る(ナディン・バルドウ)」「裁縫をテーマにしたフェミニズムアートを追求(金藤みなみ)」というように、コンセプチュアルな現代アートを制作している人でないと使えないものでもあります。
リサーチベースドアート初挑戦の人は、自分の得意分野に新しい「切り口」をかけ合わせる
ペインターや書道家など、そこまでコンセプチュアル寄りでない人の場合は、何らかの「切り口」を設定することになります。この「切り口」は難しく考える必要はありません。今回のテーマは「高倉山」という、町の中心部からすぐに行ける気軽なハイキングコースですから、「そこでの思い出話を30人分集めます」でも良いし、「毎日、同じ場所から高倉山の写真を100枚撮ります」でも良いし、「高倉山で植物標本を集めます」でも「高倉山で集めてきたXXXを使ってミクストメディア作品を作ります」でも良いのです。
昨今では安価で高性能なマイコンボードやセンサーユニットがありますから、こうした機器を自然の中に置いて観測データを収集し、それをもとに絵画や書やスカルプチャーを作ったり、それらのデジタルデータと自分の得意なビジュアルアート技法を組み合わせたインスタレーションを作るなどの提案も面白いのではないでしょうか? (広野AIR実行委員会はマイコンボード活用リサーチの技術的支援も可能です)




広野アーティスト・イン・レジデンスは特に現代アーティストとしてはキャリア初期の方々に経験値を積んでもらうこと、最初のアーティスト・イン・レジデンス実績を作ってもらうこと、広野町で繋がった他のアーティストたちとお互いに助け合って現代アーティストとしてのキャリアを続けていってもらうことを重視していますから、そこまで完成度の高い調査企画は求めていません。
ただ、アーティスト本人がその企画に興奮できているか、それともchatGPTに考えさせたものを苦し紛れに転載しているのかは、審査員に必ず伝わります。まずは自分が面白がれるかどうかを考えて調査企画を作ってください。
ナディンさん直伝! リサーチベースドアートの滞在制作企画の採択率が必ずアップする秘策
令和5年度に広野AIRで滞在制作を行ったナディン・バルドウさんのアドバイスです。
(広野AIRに限らずどこのAIRでも)現地に既にリサーチのパートナーがいる滞在制作企画は採択率が上がるそうです。ですから、思い切って公募締め切り以前に広野町に出かけて町民の方々と仲良くなり、滞在制作企画に協力しても良いよとおっしゃっていただける方を見つけるというのは、おすすめの方法です。
※ナディンさんは現在はパリでアーティスト・イン・レジデンス中です
構成はIMRADを基本にしてみよう
日本では人文学的なリサーチベースドアートがまだまだ大半ですが、自然科学・社会科学系の実証研究で用いられているIMRAD(Introduction, Method, Result And Discussion)の章構成で計画を作って提案書に落とし込むことをおすすめします。
| セクション | 内容 |
|---|---|
| Introduction | 導入部。何故このリサーチをするのか。このリサーチプロジェクトにどんな意義があるのか。 |
| Method | どのような方法でリサーチを実施するのか。人文学系の場合は文献調査、聞き取り調査、参与観察が主となる。社会科学や自然科学のアプローチを取る場合は資料・データ・試料の収集方法と分析方法を示す。 |
| Result | 学術論文においてはリサーチの結果を示す節になる。リサーチベースドアートの企画書においては「このような資料・データ・試料が集まると予想される」というものを示すと良い。 |
| Discussion | 学術論文においては前節で示されたリサーチの結果をいかに理解・解釈することが出来るかを論理的に記述する。現代アートの提案においては結果の解釈までは踏み込まず、「問い」「調査」「結果」の三つをいかに美的に洗練された形式で提示するか、そのアイデアを示すと良い。 |
何を成果物とするのか
「高倉山」がテーマだから山の絵を描きますとか、山の字を書きますというように、山の形でアウトプットすることに拘らないでください。たとえば高倉山で集めてきたXXXを顕微鏡で見たらこんな風に見えましたというリサーチベースドアートであれば、そこに山の姿はありません。でも立派な「高倉山のリサーチベースドアート」です。
最初に企画書に書いたものを必ず実現する必要はありません。それよりも広野町での滞在に夢中になって、あちこち動き回ってください。広野町で色々な人に会い、色々な場所を歩き回り、色々なものを食べてください。それを続けていったときのアーティスト自身の変化が一番大事です。アーティスト・イン・レジデンスを通して変化した自分が作品に反映されていれば、それはきっと良い作品のはずです。町民の皆さんも喜んでくれるでしょう。
「情報オーバーロード」問題に注意する
リサーチベースドアートの中でも特に人文学的アプローチでは、文献資料収集やインタビューによるリサーチが中心となります。別の言い方をするならば、一定期間どこかの地域でリサーチを実施すれば、それだけで膨大な資料がアーティストの手元に集まるということです。そしてリサーチベースドアートの成果物として1990年代から大量に作られてきたのが、そのようにして収集された資料群を展示室の中に並べてみせるインスタレーションでした。(現在でもこのスタイルの展示をする現代アーティストは珍しくありません)。
資料の並べ方や見せ方にある程度の工夫がある場合もありますが、ほとんどの観衆にとってそれは膨大な一次資料(編集が入っていない生の資料のことと考えておいてください)の山でしかありません。リサーチのプロである社会学者や文化人類学者から見ると「ただ集めた資料を並べただけのこれがなんで現代アートなの?」と思えるようなものも、当たり前に大きな公立美術館で展示されていたりします。二次資料から転記されたと思しき文章が出典を示さずに「現代アート」として展示されているものすら見たことがあります(著作権法違反です)。
全てを視聴し終わるのに何百時間もかかるビデオインタビューを会場で流し続け、全てを読み終わるまでに半年かかるような文書を並べてみせるこのような「リサーチベースドアート」は、情報オーバーロード(情報が多すぎる)作品として近年、クレア・ビショップにより批判の対象になっています。
広野町で情報オーバーロード展示をした人はまだおりません。滞在制作企画としても最終審査であまり良い点はもらえない可能性が小さくないことを指摘しておきます。
発表の前に調査協力者の了解を得る
社会学や文化人類学では基本中の基本ですが、リサーチで情報を提供していただいた協力者の方々には作品発表前に作品について詳しく説明する、内覧していただく、などの手続きが本来は必須です。そこで調査協力者からNGが出たら手直し、修正となります。学術調査の場合、苦情申し立ての手順と窓口を文書でお渡ししておくことが推奨されています。
広野AIRではこのような、調査協力者の方々による事前了承の手続きを極めて重視しますので、ご承知おきください。
最後に
リサーチベースドアートはコンピュータRPGに似ています。知らない土地に行ったらまずは徹底的に歩き回り、人に会えば話を聞き、店があれば入り、珍しいものがあれば荷物に加え、宝箱があれば開けてみるものですよね。それを広野町で徹底してやってください。そうすれば「その町で何をしたら良いのか」が自ずと見えてくるものです。
参考になるかもしれないリンク
調査倫理について
https://www.jcsw.ac.jp/img/ethics/insei_tebiki.pdf
IMRAD形式について
情報オーバーロード型展示の問題について